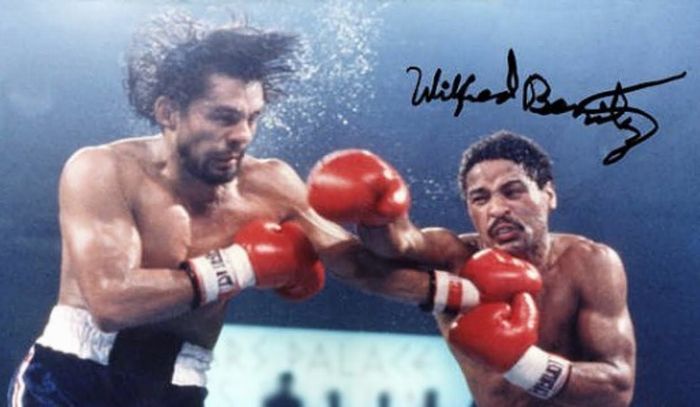アンドレ・ウォードの物語は彼が言う通り「無一文から成り上がった男、スラムから這い上がった子供みたいなありふれたストーリー」ではなく、簡単に感動、共鳴できるものではなかった。しかし、彼が戦ってきた本当の敵、抗ってきたものが何であるのか、大変興味深く、とても大事な記録だった。
魔術師の微笑み
ウォード
「ロイ・ジョーンズjr、彼はタキシードローブを着てダックテイルのヘアースタイルだった。みんな彼は間違っていると言っていた。(もう引退すべきだ)でも彼はそれをやってのけた。私は彼のそういうカッコよさ、ファッション、地方訛りの言葉遣い、自分の道を貫いたロイの姿勢が好きでした。誰も彼のような男はいませんでした。」2004年、ウォードがプロデビューする3カ月前にジョーンズはテネシー州メンフィスでのグレン・ジョンソン戦にウォードを招待した。ジョーンズはウォードに彼の金メダルをリングでつけさせてくれとお願いした。
ウォード
「控室でロイに会いました。調子は良さそうにみえました。彼は私の金メダルを身に着けました。3列目で試合を観戦しました。内容はイマイチでしたが私は信じていました。なんたってロイ・ジョーンズですから。でも彼は負けました。倒されました。ロイの息子がすぐそばで発狂していました。信じられませんでした。ロイは失神していました。その夜私はメンフィスの街を彷徨い歩いていました。失意でただ歩き回っていたのです。本当に落ち込んでいました。みんなが泊っているホテルに帰る道の途中でロールスロイスが私に近づいて止まりました。中にロイがいました。グロッキーな様子でした。私は彼を愛している、大丈夫ですかと言いましたが、本当に弱っているようでした。」
昨秋、ロイ・ジョーンズにインタビューした時、彼は神の意志で高齢になった今でも戦い続けていると言った。ならば神はまだ(全てを成しえた)アナタに一体何を求めているのかと尋ねた。
ウォード
「それは神を恐れる人が尋ねるべきいい質問です。神はあなたにNoと言ったことがありますか?神は(童話で人間の姿になって願い事をかなえてくれる)精霊ではありません。神は私にたくさんNoと言いました。それが防御メカニズムです。そういうわけでロイは長く生き延びてきたのですが、私はそれに同意することはできません。」あなたは最後の日(引退)を想像しますか?
ウォード
「毎日考えています。数学の方程式のような答えは出せないのです。伝説、財産、能力を損なうべきではありません。この3つを全て揃えたまま何人のファイターが無事に引退できたでしょうか。私は常に考えています。理解する必要があります。」ロイ・ジョーンズ
「自分がアンドレ・ウォードのローモデルであることを光栄に思います。彼は私ほど派手ではないが、私もモハメド・アリほど派手ではありませんでした。彼がコバレフを打ち負かした後もまだハングリーであるなら現役にこだわることも可能だが、もう十分だとおもいます。私がヘビー級タイトルを獲得した後(2003年のジョン・ルイスに対して)まだ戦ったのは、ただそうしたかっただけです。長い間リングに留まるのは危険です。時の経過は残酷です。」そう言いながらも、現在47歳のジョーンズはジョン・ルイス戦の後13年間も戦い続けた。
ロイ・ジョーンズ
「私にとって、アンドレ・ウォードは期待通りの優等生であり模範的な市民です。彼が上り調子の時に私がインスピレーションを与えたのであればとても嬉しくて誇らしいです。」ジョーンズの言葉をウォードに伝えると、我々は父親の妹サンディ・ブースに会いに行った。幼少時代の自分の写真をみせられてウォードは赤面していた。
サンディは兄のフランクがアフリカ系アメリカ人の妻と子供を連れてきた時の事を想い出す。
サンディ
「私たちの父はオクラホマ出身の退役軍人で人種差別主義者でした。アンドレとジョナサンをプールに連れて行った時、兄のフランクは白人の子供達の冷たい視線や差別発言から我が子を守るのにいつも必死でした。」別れを告げる際、サンディはボクシンググローブをいくつか持ってきてウォードにサインを求めた。ウォードはひどく驚いたが、叔母の頬にキスする前にこころよくサインした。
ウォードとの最後の夜、彼は別れを告げる前に2つの場所に案内してくれた。1つは彼が聖書を研究するために通っている教会だったが、もう1つが以外な場所だった。
ウォード
「もう過去は十分みてきたでしょう、今からボクシングの未来を垣間見ましょう。」ライトニングボクシングクラブでトレーニングするボクサー達は、ウォードの不意の訪問に皆一瞬で凍り付いた。しかしある一人の少年の存在が際立っていた。緑色の目をした85ポンドの12歳の少年、デイブ・ロペスがジムの中央にあるリングから我々を睨んでいた。スーパーマンがデザインされたトランクスを履いたその少年はウォードをみてニヤニヤしていた。
デイブ
「何しに来たの?ここに入ってよ。」体格同様にまだ思春期前の子供の声で叫んだ。
ウォード
「ほらね、言いませんでしたっけ?あの子をみてると昔の自分を思い出します。あの子は13歳未満で世界最高のファイターです。おーい、来たぞ!」https://www.youtube.com/watch?v=fsYXi99LUVg
ウォードはグローブをはめシャツを脱いで静かにリングに近づいた。
その時点で、ジムのほぼ全員がリングを囲んだ。
デイブは子供用のヘッドギアをつけてエプロンを登り、ウォードがリングに入れるようにロープの上に立った。
ウォード
「デイブに会いに来たんだ。ただ挨拶しに来ただけだよ。」リングに対峙するとブザーが鳴り、デイブの父親が「タイム!」と叫んだ。
次の瞬間、ボクシングの未来はボクシングの現在に襲い掛かった。
ウォードにとって、この子供は安全に遊べるおもちゃであるという幻想に怒りをぶつけるような速くて激しい攻撃だった。それを受けたウォードは特に何も抵抗しなかったが、この少年の人生におけるある種の音叉としての役割を理解していることは明らかだった。ウォードは偉大さを必要とする誰よりも多くの事を知っていた。
時にデイブはウォードをコーナーに追い込んで、鼻血を流された報復をするかのように、ウォードが鼻を守るためにガードを固めるまで、全力でパンチを打ち込んだ。ウォードの笑顔はより一層デイブを刺激した。ウォード
「もう十分かい?」デイブはより激しく襲い掛かったが、ウォードが軽いパンチを数発返すとデイブの汗を涙に変えた。
デイブの父親は息子がウォードからお墨付きをもらって感激していた。
デイブの父親
「息子がリングで自分の思い通りにならない経験をしている。彼はこの経験を一生忘れないでしょう。」ウォードが改めてスパーリングの中止を叫ぶと、まだ何もしていないとデイブが不満の声をあげた。
リングから出たウォードはコーナーの階段に座った。
「あと3年もすれば、私はこうやって彼をあしらう事ができなくなります。彼にとってはそれでいいのです。」
デイブの父親は息子を抱きしめ、鮮血に染まる鼻の手当てをしている。彼らがやってくるとウォードはデイブと腕を組み、群がる他の子供達と一緒に写真撮影のポーズをとった。笑顔を拒んだのはデイブだけだった。
デイブ
「アンドレ、今度はいつ相手をしてくれるの?」デイブがウォードに催促しているのを見て父親は微笑んだ。
ウォード
「あと何年かしたらお前の相手などやりたくないよ。でもその頃には俺はもういないさ。」そう告げてニッコリ微笑んだ。
それは魔術師の微笑みであり、彼の顔から消えた後もずっと私の心に残った。
もちろん、ウォードは他の全ての魔術師がするように、彼の秘密を解き明かすべく様々な相手に挑戦され続けてきた。
しかしおそらく、S.O.G.(神の子)アンドレ・ウォードはもうひとつの深遠な魔法を持っている。
ウォードは最高峰としてボクシングの頂点に立ち、幸福な結末(引退)で身を引くことの意味を、彼自身だけでなく他のファイター達にも伝えようとしているのだ。
ウォード以前の偉大な先人たちもみんな同じ計画を持っていたはずだ。(しかし身を滅ぼした)アンドレ・ウォードの最後の仕事と最後の敵、それが終われば、長くて苦い相続(継承=悪い結末)からボクサー達は自由を得、解放されることになるのかもしれない。
https://www.youtube.com/watch?v=E40KYyJDvQ0
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
記事の原題は
「ANDRE WARD FIGHTS TO AVOID A BOXER’S BAD ENDING」
というもので、Vol.2にもあったように
「私は悪魔を避けようとしているのです。それらの亡霊を振り払おうとしているのです。」
ボクシングの栄光と引き換えに、脳や体に障害を抱えたり、破綻したり、人生を狂わせるなんてナンセンスでクレイジーだ。アンドレ・ウォードの戦いの記録は、人生のジレンマ、忍び寄る悪魔との争いだった。遺産を築き、五体満足、平和に引退することこそ一番重要なんだと。
今まであまり語られることのなかったウォードのプライベート、白人でも黒人でもないという違和感や家族の崩壊、父親の死・・・
キャリア最後の相手が当時無敗の怪物的強打者コバレフで、そこが終着駅、そこで燃え尽きたのも、ウォードなりの計画、シナリオだったのかもしれない。ダーティーなローブローによるフィニッシュさえも計算通りのアクセント、魔法であり、セクハラ騒ぎで大暴れするコバレフとは見ている世界が違ったのかもしれない。
デューク東郷
「おれが、うさぎのように臆病だからだ…
だが…臆病のせいでこうして生きている…
虎のような男は、その勇猛さのおかげで、早死にすることになりかねない…
強すぎるのは、弱すぎるのと同様に自分の命をちぢめるものだ…」